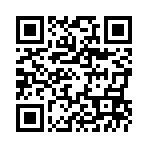2009年04月06日
実地教習五回目
今日は第二段階の実地教習一回目。つまり初路上教習でした。
前にも書いたけど、私の場合は大型免許を持っているので仮免許は不要。しかし大型車で公道を走るのは久しぶりなので緊張しました。
しかも私の通っている教習所は主要道路に出る道は事実上一本しかなく、しかもその道が大型車と普通車のすれ違いが困難な道幅しか無い区間が多く、路上一発目でここを走るだけでもかなり緊張しました。
一番キツかったのは、その狭い道で電線の工事を行っており、工事車両の脇はバスで通過不能だった事(*_*)
工事車両が移動してくれたので、何とか通る事ができましたけど・・・。
とにかく先読み先読みで走り、狭い区間や障害物のある区間は対向車を先にやり過ごさせるようにしないと、バスやタクシーでは御法度の急ブレーキを掛ける羽目になりかねない。急ブレーキは即車内事故に直結する(当然その責任は運転手が負う)ので、教習とは言えやってはいけないのだ。
しかも大型車の場合は車幅が広い上に、ミラーが高い位置で車両本体からはみ出しているので道路脇の民家の軒先とか街路樹に当たりそうになるし、普通車より遥かに気を使います。
主要道路に出れば道幅の心配はしなくて良いんだけど、コース内と違って安全確認はキッチリやらないと、普通車はもちろん平ボディ(荷台に箱の付いていない)トラック以上に死角の多いバスの場合はマジで危険が伴う。かなり緊張しながらハンドルを握っていました。
何といっても一番神経を使うのは、交差点での左折時。左後方から横断歩道に入ろうとする歩行者や自転車はミラーはもちろん目視でもほとんど見えないので、目一杯徐行しないと本当に危険。これも交差点に近づく段階であらかじめ確認が必要。右折なら後方の自転車や歩行者は目視で簡単に確認できるんですけどね。
公道をバスで走って何が一番怖いかというと、自転車と歩行者が一番怖いです。どんな動きをするか分からないし、車からは自分が見えていると思っている場合がほとんどだし、万が一の場合は責任取るのは車のほうだし・・・。
交差点も含めてこれは普通車でも同じなんだけど、普通車やトラックとは違い『急ブレーキを踏めない』という事情を抱えたバスやタクシー等旅客を乗せる車両を運転していると、周りの歩行者と自転車と車の動きに神経質にならざるを得ません。
あと、上り坂ではやはりスピードは出ませんでした。3速ではエンジンが吹け切ってしまい、4速ではトルクが不足気味で加速できない・・・という感じ。結局3速で登るんだけど、制限速度まで出せないという状態でした。後続車の皆さん、ごめんなさい。
バスならではの路上での課題として、路肩の電柱や標識や街灯をバス停に見立てて路肩停車(車両自体は本物のバスとは言え教習車は営業車両ではないので、バス停には停車禁止)・・・というものがある。
これにも「乗降口を(仮)バス停にきちんと揃えて停車し、ウィンカーはハザードにし、ギヤはニュートラルにしてクラッチを戻し、サイドブレーキを引いて、停車から発車までブレーキペダルは踏みっ放しにする」という手順がある。乗降口を開けるのは、サイドブレーキを引いた後。
(仮)バス停と乗降口を揃えるのは、コース内と勝手が違ってややズレてしまったんだけど、何とか今日のところはクリアできた。卒業検定でも必ずやるので、この辺りはしっかりできるようにならないといけない。
今日の反省点としては、制限速度を超えてしまった事が何回かあった事と、直進中に左側に寄り過ぎて路側帯のラインを踏んでしまう事が多々あった事。次回はそれを意識して修正していかねば。
で、今日二時間目の実地はシミュレーター。乗客を乗せて目的地まで乗客の指示と案内標識に従って走行するというもの。
この教習は「急ごうとする心理の悪影響」を体験する為のもので、走っていると後ろの乗客から「急いでもらえませんか?」と催促されたり、前が詰まっている状態で後ろのスポーツカーがパッシングを浴びせてきたりする。
更に、自分の走行状態に合わせて駐車車両の影から歩行者が出てきたりとか、交差点での右折時に対向車線を速度感覚が判りにくいバイクが走ってきたりとか、右または左後方の死角から歩行者が横断歩道を渡ってきたりとか・・・などなど。なかなか良くできています。
加減速と連動してシートが動いたりするけれど、Gは無いので実車の感覚で運転するのは結構難しいです。
第二段階の実地教習は、大型免許所有者の場合は10時間なんだけど、そのうちシミュレーター教習で4時間取られるので、実際に路上に出るのは6時間しかない。少ない路上教習で基本的なバスの運転をしっかりできるようにならないといけないのだが・・・。規定時間で見極めもらえるのか、ちょっと心配です(汗)
まぁ頑張るしかないんですけどね(苦笑)
 それから、これが実地教習で使っているバスでございます。先日、教習が始まる前に撮影。
それから、これが実地教習で使っているバスでございます。先日、教習が始まる前に撮影。
関西方面で実際に営業運転で使われていた車両で、中古で購入後に教習仕様に改造したもの。スピードメーター下の距離計を見てみると、走行距離は60万キロを超えています。
大型トラックではもっと走っている車両もありますが、短距離での発進→停止を繰り返すバスなので、指導員の話によると「結構各部が痛んでいる」そうです。走っている感じはあまり痛んでいる感じはしないんですけどね。
前にも書いたけど、私の場合は大型免許を持っているので仮免許は不要。しかし大型車で公道を走るのは久しぶりなので緊張しました。
しかも私の通っている教習所は主要道路に出る道は事実上一本しかなく、しかもその道が大型車と普通車のすれ違いが困難な道幅しか無い区間が多く、路上一発目でここを走るだけでもかなり緊張しました。
一番キツかったのは、その狭い道で電線の工事を行っており、工事車両の脇はバスで通過不能だった事(*_*)
工事車両が移動してくれたので、何とか通る事ができましたけど・・・。
とにかく先読み先読みで走り、狭い区間や障害物のある区間は対向車を先にやり過ごさせるようにしないと、バスやタクシーでは御法度の急ブレーキを掛ける羽目になりかねない。急ブレーキは即車内事故に直結する(当然その責任は運転手が負う)ので、教習とは言えやってはいけないのだ。
しかも大型車の場合は車幅が広い上に、ミラーが高い位置で車両本体からはみ出しているので道路脇の民家の軒先とか街路樹に当たりそうになるし、普通車より遥かに気を使います。
主要道路に出れば道幅の心配はしなくて良いんだけど、コース内と違って安全確認はキッチリやらないと、普通車はもちろん平ボディ(荷台に箱の付いていない)トラック以上に死角の多いバスの場合はマジで危険が伴う。かなり緊張しながらハンドルを握っていました。
何といっても一番神経を使うのは、交差点での左折時。左後方から横断歩道に入ろうとする歩行者や自転車はミラーはもちろん目視でもほとんど見えないので、目一杯徐行しないと本当に危険。これも交差点に近づく段階であらかじめ確認が必要。右折なら後方の自転車や歩行者は目視で簡単に確認できるんですけどね。
公道をバスで走って何が一番怖いかというと、自転車と歩行者が一番怖いです。どんな動きをするか分からないし、車からは自分が見えていると思っている場合がほとんどだし、万が一の場合は責任取るのは車のほうだし・・・。
交差点も含めてこれは普通車でも同じなんだけど、普通車やトラックとは違い『急ブレーキを踏めない』という事情を抱えたバスやタクシー等旅客を乗せる車両を運転していると、周りの歩行者と自転車と車の動きに神経質にならざるを得ません。
あと、上り坂ではやはりスピードは出ませんでした。3速ではエンジンが吹け切ってしまい、4速ではトルクが不足気味で加速できない・・・という感じ。結局3速で登るんだけど、制限速度まで出せないという状態でした。後続車の皆さん、ごめんなさい。
バスならではの路上での課題として、路肩の電柱や標識や街灯をバス停に見立てて路肩停車(車両自体は本物のバスとは言え教習車は営業車両ではないので、バス停には停車禁止)・・・というものがある。
これにも「乗降口を(仮)バス停にきちんと揃えて停車し、ウィンカーはハザードにし、ギヤはニュートラルにしてクラッチを戻し、サイドブレーキを引いて、停車から発車までブレーキペダルは踏みっ放しにする」という手順がある。乗降口を開けるのは、サイドブレーキを引いた後。
(仮)バス停と乗降口を揃えるのは、コース内と勝手が違ってややズレてしまったんだけど、何とか今日のところはクリアできた。卒業検定でも必ずやるので、この辺りはしっかりできるようにならないといけない。
今日の反省点としては、制限速度を超えてしまった事が何回かあった事と、直進中に左側に寄り過ぎて路側帯のラインを踏んでしまう事が多々あった事。次回はそれを意識して修正していかねば。
で、今日二時間目の実地はシミュレーター。乗客を乗せて目的地まで乗客の指示と案内標識に従って走行するというもの。
この教習は「急ごうとする心理の悪影響」を体験する為のもので、走っていると後ろの乗客から「急いでもらえませんか?」と催促されたり、前が詰まっている状態で後ろのスポーツカーがパッシングを浴びせてきたりする。
更に、自分の走行状態に合わせて駐車車両の影から歩行者が出てきたりとか、交差点での右折時に対向車線を速度感覚が判りにくいバイクが走ってきたりとか、右または左後方の死角から歩行者が横断歩道を渡ってきたりとか・・・などなど。なかなか良くできています。
加減速と連動してシートが動いたりするけれど、Gは無いので実車の感覚で運転するのは結構難しいです。
第二段階の実地教習は、大型免許所有者の場合は10時間なんだけど、そのうちシミュレーター教習で4時間取られるので、実際に路上に出るのは6時間しかない。少ない路上教習で基本的なバスの運転をしっかりできるようにならないといけないのだが・・・。規定時間で見極めもらえるのか、ちょっと心配です(汗)
まぁ頑張るしかないんですけどね(苦笑)
 それから、これが実地教習で使っているバスでございます。先日、教習が始まる前に撮影。
それから、これが実地教習で使っているバスでございます。先日、教習が始まる前に撮影。関西方面で実際に営業運転で使われていた車両で、中古で購入後に教習仕様に改造したもの。スピードメーター下の距離計を見てみると、走行距離は60万キロを超えています。
大型トラックではもっと走っている車両もありますが、短距離での発進→停止を繰り返すバスなので、指導員の話によると「結構各部が痛んでいる」そうです。走っている感じはあまり痛んでいる感じはしないんですけどね。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。