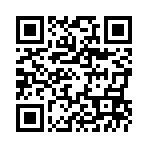2009年04月21日
ようやく取得
免許証の交付を受け、先程帰宅しました。今回からICチップの入った免許証になりましたが、それと同時にようやく金色免許になりました。
 とりあえず証拠画像。
とりあえず証拠画像。
免許区分に「普通」が無くて「中型」と入ってますが、もちろん中型免許を新たに取ったわけではなく、以前の普通免許のおまけ。
後は大型特殊と牽引免許を取ればほとんどの車種をカバーできるんだけど、今の所は取得予定無し。まぁ機会があったらという事で・・・。
他にも牽引二種(トレーラーバス・「連接バス」とも言う)とか大型特殊二種(雪上車のバス)があるんだけど、車両自体が極端に少ないし、これらは免許試験場での外来試験しかないので取る機会も無いでしょう。
今回の大型二種免許取得で、世間ではあまり高く評価されていないタクシーやバスの運転手が、自分の車を自分で運転しているのと違って実は大変な状況・環境で運転しているという事、そして自分を含めた普通車のドライバーが、いかに自分本位の運転をしているかがよく分かりました。
とにかく、自分の運転を見直す良い機会になりました。
しかし、一つ不満な所があったりします。それは、免許証の顔写真(^_^;)
普通免許を取って以来、免許証の顔写真で納得できる写りだった事って一度も無いんですよねぇ・・・。何故なんでしょう?
 とりあえず証拠画像。
とりあえず証拠画像。免許区分に「普通」が無くて「中型」と入ってますが、もちろん中型免許を新たに取ったわけではなく、以前の普通免許のおまけ。
後は大型特殊と牽引免許を取ればほとんどの車種をカバーできるんだけど、今の所は取得予定無し。まぁ機会があったらという事で・・・。
他にも牽引二種(トレーラーバス・「連接バス」とも言う)とか大型特殊二種(雪上車のバス)があるんだけど、車両自体が極端に少ないし、これらは免許試験場での外来試験しかないので取る機会も無いでしょう。
今回の大型二種免許取得で、世間ではあまり高く評価されていないタクシーやバスの運転手が、自分の車を自分で運転しているのと違って実は大変な状況・環境で運転しているという事、そして自分を含めた普通車のドライバーが、いかに自分本位の運転をしているかがよく分かりました。
とにかく、自分の運転を見直す良い機会になりました。
しかし、一つ不満な所があったりします。それは、免許証の顔写真(^_^;)
普通免許を取って以来、免許証の顔写真で納得できる写りだった事って一度も無いんですよねぇ・・・。何故なんでしょう?
2009年04月20日
学科試験
明日、学科試験を受けに行きます。
受付は朝8時半からなんだけど、場所が自宅から1時間半くらいかかる場所なんで、遅くとも朝6時には出発しなければならない。という訳で、明日は早起きしなきゃなりません。
受験勉強のほうは、とりあえず問題集を中心にやってきました。だいたい1000問程度やりましたが、まだ自信を持つまでには至っていません。
試験開始直前まで問題集や学科教本を見ながら勉強しますが、できるだけの事はやってみます。
受付は朝8時半からなんだけど、場所が自宅から1時間半くらいかかる場所なんで、遅くとも朝6時には出発しなければならない。という訳で、明日は早起きしなきゃなりません。
受験勉強のほうは、とりあえず問題集を中心にやってきました。だいたい1000問程度やりましたが、まだ自信を持つまでには至っていません。
試験開始直前まで問題集や学科教本を見ながら勉強しますが、できるだけの事はやってみます。
2009年04月18日
やっと合格
今日は3回目の卒検でしたが、やっと合格できました。
路上が1回目と同じコース、コース内課題は2回目と同じコース。路上は交通量が多い中、とにかく今まで指摘されてきた事を注意しつつ走り、コース内課題は特に後方間隔であまり寄せすぎないように注意して車体を誘導しました。
同期で入学した人と一緒でしたが2人とも無事合格でき、卒業証明書と学科試験の受験票を貰ってきました。
これで一つの山場は越えました。あとは学科試験。
しかし地元では試験が月一回しか無く次回は来月になってしまう為、時間に余裕の無い私は県の運転免許試験場で受験する予定です。
路上が1回目と同じコース、コース内課題は2回目と同じコース。路上は交通量が多い中、とにかく今まで指摘されてきた事を注意しつつ走り、コース内課題は特に後方間隔であまり寄せすぎないように注意して車体を誘導しました。
同期で入学した人と一緒でしたが2人とも無事合格でき、卒業証明書と学科試験の受験票を貰ってきました。
これで一つの山場は越えました。あとは学科試験。
しかし地元では試験が月一回しか無く次回は来月になってしまう為、時間に余裕の無い私は県の運転免許試験場で受験する予定です。
2009年04月16日
卒検二回目
結果から言うと・・・今回も不合格でした。
今回は前回とは違うコース。検定員も違う人。前回は路上では大きなミスは無かったんだけど、今回は交差点を黄信号で突っ込みそうになってしまい、かなり強いブレーキで無理やり止まる羽目になってしまった。急ブレーキは、タクシーやバスでは基本的にやってはいけない行為。
試験管曰く、「それでも黄信号を突っ切ってしまうよりは良い」という事なんだけど・・・。
原因は信号のある交差点が二つ続いている場所で向こう側の信号に目が行ってしまい、手前交差点の歩行者用信号の点滅に気が付かなかった事。
あと路端からの発進と交差点の右左折時の、リヤオーバーハング外側振り出しの注意が不足しているとの事。
しかし一番の大きなミスは、縦列駐車時の後方間隔。縦列駐車で車体を所定の位置に入れ、運転席から10メートル後方にあるリヤバンパーと後方ポールを50cm以内にするべくじりじりと後退していて、リヤバンパーがポールに接触してしまったのだ。
例えそれまで路上を含めて減点無しでも、これをやったら一発で不合格。ちなみにこれも、今回の卒業検定での最終課題で、昨日はバッチリできた課題でした。
完全に自信喪失しています。いくら練習で上手くできても、本番(検定)でできなければ意味が無い。我ながら全く度し難い人間と思う。補習教習は今日済ませてきたんだけど、全く自信に結びつかない状態。
次回の卒検は明後日。一日空くし自信が持てないので、やるだけやってみる・・・としか言えません。
とりあえず今日は疲れたので、早々と寝ます。別件でメールも貰っているんだけど、返信はもう少し待っててください。
今回は前回とは違うコース。検定員も違う人。前回は路上では大きなミスは無かったんだけど、今回は交差点を黄信号で突っ込みそうになってしまい、かなり強いブレーキで無理やり止まる羽目になってしまった。急ブレーキは、タクシーやバスでは基本的にやってはいけない行為。
試験管曰く、「それでも黄信号を突っ切ってしまうよりは良い」という事なんだけど・・・。
原因は信号のある交差点が二つ続いている場所で向こう側の信号に目が行ってしまい、手前交差点の歩行者用信号の点滅に気が付かなかった事。
あと路端からの発進と交差点の右左折時の、リヤオーバーハング外側振り出しの注意が不足しているとの事。
しかし一番の大きなミスは、縦列駐車時の後方間隔。縦列駐車で車体を所定の位置に入れ、運転席から10メートル後方にあるリヤバンパーと後方ポールを50cm以内にするべくじりじりと後退していて、リヤバンパーがポールに接触してしまったのだ。
例えそれまで路上を含めて減点無しでも、これをやったら一発で不合格。ちなみにこれも、今回の卒業検定での最終課題で、昨日はバッチリできた課題でした。
完全に自信喪失しています。いくら練習で上手くできても、本番(検定)でできなければ意味が無い。我ながら全く度し難い人間と思う。補習教習は今日済ませてきたんだけど、全く自信に結びつかない状態。
次回の卒検は明後日。一日空くし自信が持てないので、やるだけやってみる・・・としか言えません。
とりあえず今日は疲れたので、早々と寝ます。別件でメールも貰っているんだけど、返信はもう少し待っててください。
2009年04月15日
卒検
昨日は卒検だったんだけど・・・不合格でした(-_-;)
路上は特に大きな問題は無かったそうなんだけど、コース内課題の一つ・方向転換が自分でも呆れるくらいにダメでした。一昨日の教習最終日は一発でできた課題です。
バックして規定の場所に収め、後方間隔(バックモニター無しで後方のポールから50cm以内まで寄せる)を済ませたまでは良いんだけど、そこから出るのに何回も切り返しをする羽目になってしまい、結局は出られたんだけど「通過不能」を取られてしまいました。
検定の一番最後の課題で、それさえ無ければ十分に合格してたそうです。(ちなみに私の通っている教習所では、大型と大型二種の卒検は路上が先で、コース内課題は路上検定後に行う方法になってます。だから不合格は確定していましたが、完走はできました)
鋭角コースのような二種特有の課題ならともかく、難易度は違えど普通免許の教習でもある課題で大失敗するとは、我ながら情け無い・・・。補習教習の予約を済ませて帰宅してからしばらくの間は、自己嫌悪の塊のような状態でした。
それにしても・・・緊張していなかったと言えば嘘になるけど、ガチガチになるまで緊張していたわけでもない。とは言え、やはり焦りが出たんだろうなぁ・・・。今にして考えてみると、ハンドルを切り始めるタイミング(当然普通車とは全然違う)が早かった感じだし・・・。
という訳で、今日は補習実地教習でした。指導員は検定の時とは別の方だったんだけど、やって来て最初の一言が、「あれ? ○○(本名)さん、どうしちゃったんですか?」でした。(滝汗)
補修教習の内容は、そんな訳で路上には出ずにコース内課題の方向転換・鋭角コース・縦列駐車を繰り返し練習しました。
明日は二度目の卒検。頑張ります。
路上は特に大きな問題は無かったそうなんだけど、コース内課題の一つ・方向転換が自分でも呆れるくらいにダメでした。一昨日の教習最終日は一発でできた課題です。
バックして規定の場所に収め、後方間隔(バックモニター無しで後方のポールから50cm以内まで寄せる)を済ませたまでは良いんだけど、そこから出るのに何回も切り返しをする羽目になってしまい、結局は出られたんだけど「通過不能」を取られてしまいました。
検定の一番最後の課題で、それさえ無ければ十分に合格してたそうです。(ちなみに私の通っている教習所では、大型と大型二種の卒検は路上が先で、コース内課題は路上検定後に行う方法になってます。だから不合格は確定していましたが、完走はできました)
鋭角コースのような二種特有の課題ならともかく、難易度は違えど普通免許の教習でもある課題で大失敗するとは、我ながら情け無い・・・。補習教習の予約を済ませて帰宅してからしばらくの間は、自己嫌悪の塊のような状態でした。
それにしても・・・緊張していなかったと言えば嘘になるけど、ガチガチになるまで緊張していたわけでもない。とは言え、やはり焦りが出たんだろうなぁ・・・。今にして考えてみると、ハンドルを切り始めるタイミング(当然普通車とは全然違う)が早かった感じだし・・・。
という訳で、今日は補習実地教習でした。指導員は検定の時とは別の方だったんだけど、やって来て最初の一言が、「あれ? ○○(本名)さん、どうしちゃったんですか?」でした。(滝汗)
補修教習の内容は、そんな訳で路上には出ずにコース内課題の方向転換・鋭角コース・縦列駐車を繰り返し練習しました。
明日は二度目の卒検。頑張ります。
2009年04月11日
実地教習八回目
昨日は路上1時間と、シミュレーター1時間やってきました。
路上は「山岳走行」というやつで、いつものコースとは違う道を走りました。もちろん私が普通免許を取った頃には無かった課題で、ネットで調べたら地域に合わせた内容という事で、地域毎あるいは教習所毎に内容が若干変わってくるのだそうな。
私の通っている教習所の山岳コースはアップダウンとカーブの多い農道が設定されており、道幅は路線バスだとセンターラインや路側帯をかろうじて踏まずに走行できる、という感じ。道の両側は果樹園が多いので、道にはみ出している枝を時々避けながら走る事になる。
もちろん制限速度を大きく下回るような走りはできないので、走行位置を両側ミラーで確認しつつ結構緊張しながら走りました。
もっとも、制限速度で走っていても後続車が数珠繋ぎになってしまうので(苦笑)、時々目一杯左に寄って追い抜かせたりしながらの教習でした。
2時間目のシミュレーターは悪条件下での走行で、雨&雪道&横風&濃霧といったメニュー。雪道では前走車がいきなりスリップして車体が斜めになったりするので、こちらも慎重にハンドルとブレーキを操作したのだが、思ったよりスリップせずに拍子抜け。
一番面食らったのは横風で、トンネルを抜けた途端に思いっきり画面が左右に揺れて、シミュレーターはそれほど苦手でもない私もさすがに目がクラクラしました。基本的に進路を微調整しながら走ればOKだけど、前を走っているトラックの積荷が風でバタバタ煽られているので、それに注意しなければならない。
濃霧はほとんど前が見えない状態での運転になるので、路側帯のラインを目安に速度を落として走れば、突然の障害物にも対処できるでしょう。ちなみに濃霧モードでは、全ての対向車がカーブでセンターラインをはみ出してきます(苦笑)。
シミュレーターはこれで全て終了したので、残すは路上2時間のみ。その2時間で卒検に合格できるレベルになっておかないと・・・。
私が苦手としている路端停車なんだけど、指導員から非常にありがたいアドバイスも頂いた。仮想停留所と乗降口を一発で合わせられるように頑張ります。
路上は「山岳走行」というやつで、いつものコースとは違う道を走りました。もちろん私が普通免許を取った頃には無かった課題で、ネットで調べたら地域に合わせた内容という事で、地域毎あるいは教習所毎に内容が若干変わってくるのだそうな。
私の通っている教習所の山岳コースはアップダウンとカーブの多い農道が設定されており、道幅は路線バスだとセンターラインや路側帯をかろうじて踏まずに走行できる、という感じ。道の両側は果樹園が多いので、道にはみ出している枝を時々避けながら走る事になる。
もちろん制限速度を大きく下回るような走りはできないので、走行位置を両側ミラーで確認しつつ結構緊張しながら走りました。
もっとも、制限速度で走っていても後続車が数珠繋ぎになってしまうので(苦笑)、時々目一杯左に寄って追い抜かせたりしながらの教習でした。
2時間目のシミュレーターは悪条件下での走行で、雨&雪道&横風&濃霧といったメニュー。雪道では前走車がいきなりスリップして車体が斜めになったりするので、こちらも慎重にハンドルとブレーキを操作したのだが、思ったよりスリップせずに拍子抜け。
一番面食らったのは横風で、トンネルを抜けた途端に思いっきり画面が左右に揺れて、シミュレーターはそれほど苦手でもない私もさすがに目がクラクラしました。基本的に進路を微調整しながら走ればOKだけど、前を走っているトラックの積荷が風でバタバタ煽られているので、それに注意しなければならない。
濃霧はほとんど前が見えない状態での運転になるので、路側帯のラインを目安に速度を落として走れば、突然の障害物にも対処できるでしょう。ちなみに濃霧モードでは、全ての対向車がカーブでセンターラインをはみ出してきます(苦笑)。
シミュレーターはこれで全て終了したので、残すは路上2時間のみ。その2時間で卒検に合格できるレベルになっておかないと・・・。
私が苦手としている路端停車なんだけど、指導員から非常にありがたいアドバイスも頂いた。仮想停留所と乗降口を一発で合わせられるように頑張ります。
2009年04月09日
第二段階学科・二日目
最大の山場も何とか終了。今日は学科6時間&実地3時間でした。
もっとも実地3時間のうち2時間はシミュレーターで、残りの1時間もセット教習だったので実質的に運転したのは半分だったんだけど。
その1時間の路上教習は、コメンタリードライビングという奴でした。これは見たものや感じた事や注意している点をそのつど言葉に出して実況しながら走る、というもの。
最初は照れが入るけど、慣れればそれなりに実況できるようになります。さすがに狭路では実況する余裕が無くなってきますが(^_^;)
シミュレーターも、慣れてきたとは言え車両感覚が実車と全然違うので、正直言って目が疲れます。セット教習の相方の人はシミュレーターが苦手なので、気分が悪くなってきたそうですが・・・。
路上では今回もちょいとミスがあり、反省点もあります。実地教習は残り4時間なんだけど、そのうちシミュレーターが1時間なので、実質残り3時間。何とかスムーズな運転ができるように頑張ろうとは思うけど、気持ちばっかり先走りしている感じ。
明日からは時間的に少し余裕ができるので、実地の教本を見ながらイメージトレーニングしようと思います。
もっとも実地3時間のうち2時間はシミュレーターで、残りの1時間もセット教習だったので実質的に運転したのは半分だったんだけど。
その1時間の路上教習は、コメンタリードライビングという奴でした。これは見たものや感じた事や注意している点をそのつど言葉に出して実況しながら走る、というもの。
最初は照れが入るけど、慣れればそれなりに実況できるようになります。さすがに狭路では実況する余裕が無くなってきますが(^_^;)
シミュレーターも、慣れてきたとは言え車両感覚が実車と全然違うので、正直言って目が疲れます。セット教習の相方の人はシミュレーターが苦手なので、気分が悪くなってきたそうですが・・・。
路上では今回もちょいとミスがあり、反省点もあります。実地教習は残り4時間なんだけど、そのうちシミュレーターが1時間なので、実質残り3時間。何とかスムーズな運転ができるように頑張ろうとは思うけど、気持ちばっかり先走りしている感じ。
明日からは時間的に少し余裕ができるので、実地の教本を見ながらイメージトレーニングしようと思います。
2009年04月08日
第二段階学科・一日目
今日は第二段階の学科を一日中やってました。主な内容は応急救護処置。
私が免許を取った頃と違って今は普通免許でもやるみたいだけど、二種の場合は昔から義務付けられていたので、応急救護処置の実習がある事は知っていました。
最初の2時間は講義&DVDでの座学。残りの4時間は応急救護処置の実習でした。実習には、知っている人も多いと思うけど人工呼吸と心臓マッサージ練習用の人形を使う。
以前は脈を見たりとかしたようなんだけど、今は呼吸の有無を確認して、呼吸が止まっていたら人工呼吸も心臓マッサージも両方やるとの事。心臓マッサージで押す位置も、以前はみぞおちから指の幅二本分上の位置を押す・・・というものらしかったけれど、今は乳頭を結んだ線の中央部を押す、と簡易的になってます。
なぜかと言うと、一分一秒を争うので脈を確認したり押す位置を確認している暇があったら、とっとと救護処置をしなさいという事です。
まず人工呼吸を2回、その次に心臓マッサージを30回、そして人工呼吸をもう2回。それでも蘇生しない場合は、人工呼吸2回と心臓マッサージ30回を1セットとして、より高度な処置ができる救急隊が駆けつけるまで繰り返します。
息を吹き込む量や心臓マッサージ時に押す位置や量やリズムはモニターされていて、結果をプリントアウトしてくれるのだが、やってみると結構難しい。
息は沢山吹き込めば良いというものでは無いし、押す位置・量はもちろん押す方向も決められている。また体力も結構使うので、何回かやっていると額に汗がダラダラと流れる状態。
けど交通事故でなくても役に立つ場面はあるわけだし、二種免許を取るつもりの無い人も一度講習に参加するのも十分に意義があると思います。
人工呼吸というと抵抗のある人も結構多いと思うけど、今回は透明フィルムにワンウェイバルブ(逆流防止バルブ)の付いた専用器具を使ってやりました。人工呼吸の補助器具は何種類か出ているそうですが、これは助けられる人が感染症を持っていないという保証は無い、という理由からです。
あと、AEDの使い方も教えていただきました。昔は電気ショックで蘇生と言うと大掛かりな装置を使って医師と看護師が行うもの・・・というイメージだったけど、今は取り扱いが簡単なんですねぇ。コンパクトで持ち運びも楽だし、操作方法は音声ガイダンス付きだし、電気ショックが必要かどうかも自動で判断してくれるし。
今日は、なかなか良い経験ができました。
余談ですが、指導員の話によると男性が女性に応急救護処置を施した場合、助ける男性側が助けられた女性側からセクハラ訴訟を起こされる事もあるのだとか(汗) 一番怖いと言うか厄介なのは、それなのかもしれません。
明日は学科と実地の両方が、朝9時頃から夜7時過ぎまでみっちり入ってます。二種の場合学科は同期で入校した人が全員揃って一緒にやっているんだけど、明日の学科はシミュレーターを含めて4時間で、一緒に大型二種の教習を受けている人とのセット教習です。これも初めての経験。
セット教習の相方になる人とは今日も学科を一緒にやったんだけど、気が合う人だしお互いに良い刺激になって技量向上できれば良いな・・・と思っています。
私が免許を取った頃と違って今は普通免許でもやるみたいだけど、二種の場合は昔から義務付けられていたので、応急救護処置の実習がある事は知っていました。
最初の2時間は講義&DVDでの座学。残りの4時間は応急救護処置の実習でした。実習には、知っている人も多いと思うけど人工呼吸と心臓マッサージ練習用の人形を使う。
以前は脈を見たりとかしたようなんだけど、今は呼吸の有無を確認して、呼吸が止まっていたら人工呼吸も心臓マッサージも両方やるとの事。心臓マッサージで押す位置も、以前はみぞおちから指の幅二本分上の位置を押す・・・というものらしかったけれど、今は乳頭を結んだ線の中央部を押す、と簡易的になってます。
なぜかと言うと、一分一秒を争うので脈を確認したり押す位置を確認している暇があったら、とっとと救護処置をしなさいという事です。
まず人工呼吸を2回、その次に心臓マッサージを30回、そして人工呼吸をもう2回。それでも蘇生しない場合は、人工呼吸2回と心臓マッサージ30回を1セットとして、より高度な処置ができる救急隊が駆けつけるまで繰り返します。
息を吹き込む量や心臓マッサージ時に押す位置や量やリズムはモニターされていて、結果をプリントアウトしてくれるのだが、やってみると結構難しい。
息は沢山吹き込めば良いというものでは無いし、押す位置・量はもちろん押す方向も決められている。また体力も結構使うので、何回かやっていると額に汗がダラダラと流れる状態。
けど交通事故でなくても役に立つ場面はあるわけだし、二種免許を取るつもりの無い人も一度講習に参加するのも十分に意義があると思います。
人工呼吸というと抵抗のある人も結構多いと思うけど、今回は透明フィルムにワンウェイバルブ(逆流防止バルブ)の付いた専用器具を使ってやりました。人工呼吸の補助器具は何種類か出ているそうですが、これは助けられる人が感染症を持っていないという保証は無い、という理由からです。
あと、AEDの使い方も教えていただきました。昔は電気ショックで蘇生と言うと大掛かりな装置を使って医師と看護師が行うもの・・・というイメージだったけど、今は取り扱いが簡単なんですねぇ。コンパクトで持ち運びも楽だし、操作方法は音声ガイダンス付きだし、電気ショックが必要かどうかも自動で判断してくれるし。
今日は、なかなか良い経験ができました。
余談ですが、指導員の話によると男性が女性に応急救護処置を施した場合、助ける男性側が助けられた女性側からセクハラ訴訟を起こされる事もあるのだとか(汗) 一番怖いと言うか厄介なのは、それなのかもしれません。
明日は学科と実地の両方が、朝9時頃から夜7時過ぎまでみっちり入ってます。二種の場合学科は同期で入校した人が全員揃って一緒にやっているんだけど、明日の学科はシミュレーターを含めて4時間で、一緒に大型二種の教習を受けている人とのセット教習です。これも初めての経験。
セット教習の相方になる人とは今日も学科を一緒にやったんだけど、気が合う人だしお互いに良い刺激になって技量向上できれば良いな・・・と思っています。
2009年04月07日
実地教習六回目
自分で言うのも何なんだけど、今日の路上教習はまるっきりダメダメでした(-_-;)
まず、「バス停に乗降口を合わせて止める」という必須の課題がどうにもうまくいかなかった。原因は、きちんと合わせた場合の運転席からの仮バス停の見え方を、十分に把握していなかった事と、ミラーだけで位置を合わせようとしていた事。
対応策としては、運転席からの見え方を把握する事と、それに伴って直接目視で位置合わせする事。ただし、目視の場合はほとんど後ろを上半身ごと振り返る形になるので、注視してはいけない。思いっきり徐行した上でチラッと見るだけにしないと、前方不注意で減点になってしまうし、だいいち危険。この辺りの兼ね合いが難しいんだけど・・・。
それから、私には一つの方向に注意が行きやすい傾向があるようで、今日は指導員にブレーキを踏まれる事二回。(ダメじゃん・・・自分)
対応策としては、特に交差点での右左折時は前方だけではなく常に全方位に注意を振り向ける事なのだが、頭では分かっていても死角の多い大型車の場合は、これがなかなか大変。
後方リヤオーバーハングの外側への振り出しに注意しつつ、前方対向車に注意しつつ、横断歩道上の歩行者や自転車に注意しつつ、左折時はバイクや自転車の巻き込みに注意しつつ、内側後輪の縁石接触に注意しつつ、よくいる停止線をはみ出して止まっている車両に注意しつつ、車内の乗客の様子にも注意しつつ・・・等々。
これ全部を、同時進行でやらなければなりません。
あと今日の路上教習で疲れたのは、それだけではありません。
四輪は普通免許しか無いドライバーが多いわけだけど、そういったドライバーは大型車の特性、ましてやバスの特性や走行中の事情なんて知らない(もしくは教わっても忘れている)し、大型二種の路上の課題なんて知らない人がほとんど。大型二種の路上教習と出くわす機会も少ないし。
路肩の電柱や街灯をバス停に見立てて路肩停車しなければならないけど、その時に後ろからクラクションを鳴らされる事も。交通量が多い場所でもやるので尚更。こちらとしては、決められた事を必要に迫られてやっているので、クラクションを鳴らされても困ってしまうんですね。もちろん気持ちは分かるけど・・・。
ここを見ている方は、教習所の大型バスが路肩に止まっていたら路上課題をやっていると思われるので、邪魔かもしれないけど大目に見てやってください。必要性があってやっている事ですし、バス停では無い所で路肩停車するので車間距離は多く取って下さいね。
それから、教習で使っているバス本体なんだけど、クラッチの繋がる位置が変化するのにも参りました。
特に教習後半になると、クラッチペダルをかなり戻さないと繋がらなくなる傾向があるんですね。それならそれで位置が一定ならいいんですけど、クラッチ操作をする度に繋がる位置が微妙に変わるという・・・(T_T)
特に登りの狭い道で対向車とすれ違う時に、微妙に車体を前進させる時にクラッチの繋がるタイミングが遅れる事があり、その場合は車体が後ずさりするのでかなり冷や汗ものです。もちろん減点対象ですし、真後ろが全く見えない大型車の場合は危険なわけです。
私の通っている教習所の教習バスは営業運転で散々走り込んだ中古車だし、一台しかないので文句を言ってはいけないんだけど、なかなか慣れません。まぁこれも練習の一環、と思うようにはしていますが・・・。
明日・明後日は、第二段階の学科と実地が一日中まとめて入っている怒涛の二日間になるので、何とか頑張って乗り切ります。
まず、「バス停に乗降口を合わせて止める」という必須の課題がどうにもうまくいかなかった。原因は、きちんと合わせた場合の運転席からの仮バス停の見え方を、十分に把握していなかった事と、ミラーだけで位置を合わせようとしていた事。
対応策としては、運転席からの見え方を把握する事と、それに伴って直接目視で位置合わせする事。ただし、目視の場合はほとんど後ろを上半身ごと振り返る形になるので、注視してはいけない。思いっきり徐行した上でチラッと見るだけにしないと、前方不注意で減点になってしまうし、だいいち危険。この辺りの兼ね合いが難しいんだけど・・・。
それから、私には一つの方向に注意が行きやすい傾向があるようで、今日は指導員にブレーキを踏まれる事二回。(ダメじゃん・・・自分)
対応策としては、特に交差点での右左折時は前方だけではなく常に全方位に注意を振り向ける事なのだが、頭では分かっていても死角の多い大型車の場合は、これがなかなか大変。
後方リヤオーバーハングの外側への振り出しに注意しつつ、前方対向車に注意しつつ、横断歩道上の歩行者や自転車に注意しつつ、左折時はバイクや自転車の巻き込みに注意しつつ、内側後輪の縁石接触に注意しつつ、よくいる停止線をはみ出して止まっている車両に注意しつつ、車内の乗客の様子にも注意しつつ・・・等々。
これ全部を、同時進行でやらなければなりません。
あと今日の路上教習で疲れたのは、それだけではありません。
四輪は普通免許しか無いドライバーが多いわけだけど、そういったドライバーは大型車の特性、ましてやバスの特性や走行中の事情なんて知らない(もしくは教わっても忘れている)し、大型二種の路上の課題なんて知らない人がほとんど。大型二種の路上教習と出くわす機会も少ないし。
路肩の電柱や街灯をバス停に見立てて路肩停車しなければならないけど、その時に後ろからクラクションを鳴らされる事も。交通量が多い場所でもやるので尚更。こちらとしては、決められた事を必要に迫られてやっているので、クラクションを鳴らされても困ってしまうんですね。もちろん気持ちは分かるけど・・・。
ここを見ている方は、教習所の大型バスが路肩に止まっていたら路上課題をやっていると思われるので、邪魔かもしれないけど大目に見てやってください。必要性があってやっている事ですし、バス停では無い所で路肩停車するので車間距離は多く取って下さいね。
それから、教習で使っているバス本体なんだけど、クラッチの繋がる位置が変化するのにも参りました。
特に教習後半になると、クラッチペダルをかなり戻さないと繋がらなくなる傾向があるんですね。それならそれで位置が一定ならいいんですけど、クラッチ操作をする度に繋がる位置が微妙に変わるという・・・(T_T)
特に登りの狭い道で対向車とすれ違う時に、微妙に車体を前進させる時にクラッチの繋がるタイミングが遅れる事があり、その場合は車体が後ずさりするのでかなり冷や汗ものです。もちろん減点対象ですし、真後ろが全く見えない大型車の場合は危険なわけです。
私の通っている教習所の教習バスは営業運転で散々走り込んだ中古車だし、一台しかないので文句を言ってはいけないんだけど、なかなか慣れません。まぁこれも練習の一環、と思うようにはしていますが・・・。
明日・明後日は、第二段階の学科と実地が一日中まとめて入っている怒涛の二日間になるので、何とか頑張って乗り切ります。
2009年04月06日
実地教習五回目
今日は第二段階の実地教習一回目。つまり初路上教習でした。
前にも書いたけど、私の場合は大型免許を持っているので仮免許は不要。しかし大型車で公道を走るのは久しぶりなので緊張しました。
しかも私の通っている教習所は主要道路に出る道は事実上一本しかなく、しかもその道が大型車と普通車のすれ違いが困難な道幅しか無い区間が多く、路上一発目でここを走るだけでもかなり緊張しました。
一番キツかったのは、その狭い道で電線の工事を行っており、工事車両の脇はバスで通過不能だった事(*_*)
工事車両が移動してくれたので、何とか通る事ができましたけど・・・。
とにかく先読み先読みで走り、狭い区間や障害物のある区間は対向車を先にやり過ごさせるようにしないと、バスやタクシーでは御法度の急ブレーキを掛ける羽目になりかねない。急ブレーキは即車内事故に直結する(当然その責任は運転手が負う)ので、教習とは言えやってはいけないのだ。
しかも大型車の場合は車幅が広い上に、ミラーが高い位置で車両本体からはみ出しているので道路脇の民家の軒先とか街路樹に当たりそうになるし、普通車より遥かに気を使います。
主要道路に出れば道幅の心配はしなくて良いんだけど、コース内と違って安全確認はキッチリやらないと、普通車はもちろん平ボディ(荷台に箱の付いていない)トラック以上に死角の多いバスの場合はマジで危険が伴う。かなり緊張しながらハンドルを握っていました。
何といっても一番神経を使うのは、交差点での左折時。左後方から横断歩道に入ろうとする歩行者や自転車はミラーはもちろん目視でもほとんど見えないので、目一杯徐行しないと本当に危険。これも交差点に近づく段階であらかじめ確認が必要。右折なら後方の自転車や歩行者は目視で簡単に確認できるんですけどね。
公道をバスで走って何が一番怖いかというと、自転車と歩行者が一番怖いです。どんな動きをするか分からないし、車からは自分が見えていると思っている場合がほとんどだし、万が一の場合は責任取るのは車のほうだし・・・。
交差点も含めてこれは普通車でも同じなんだけど、普通車やトラックとは違い『急ブレーキを踏めない』という事情を抱えたバスやタクシー等旅客を乗せる車両を運転していると、周りの歩行者と自転車と車の動きに神経質にならざるを得ません。
あと、上り坂ではやはりスピードは出ませんでした。3速ではエンジンが吹け切ってしまい、4速ではトルクが不足気味で加速できない・・・という感じ。結局3速で登るんだけど、制限速度まで出せないという状態でした。後続車の皆さん、ごめんなさい。
バスならではの路上での課題として、路肩の電柱や標識や街灯をバス停に見立てて路肩停車(車両自体は本物のバスとは言え教習車は営業車両ではないので、バス停には停車禁止)・・・というものがある。
これにも「乗降口を(仮)バス停にきちんと揃えて停車し、ウィンカーはハザードにし、ギヤはニュートラルにしてクラッチを戻し、サイドブレーキを引いて、停車から発車までブレーキペダルは踏みっ放しにする」という手順がある。乗降口を開けるのは、サイドブレーキを引いた後。
(仮)バス停と乗降口を揃えるのは、コース内と勝手が違ってややズレてしまったんだけど、何とか今日のところはクリアできた。卒業検定でも必ずやるので、この辺りはしっかりできるようにならないといけない。
今日の反省点としては、制限速度を超えてしまった事が何回かあった事と、直進中に左側に寄り過ぎて路側帯のラインを踏んでしまう事が多々あった事。次回はそれを意識して修正していかねば。
で、今日二時間目の実地はシミュレーター。乗客を乗せて目的地まで乗客の指示と案内標識に従って走行するというもの。
この教習は「急ごうとする心理の悪影響」を体験する為のもので、走っていると後ろの乗客から「急いでもらえませんか?」と催促されたり、前が詰まっている状態で後ろのスポーツカーがパッシングを浴びせてきたりする。
更に、自分の走行状態に合わせて駐車車両の影から歩行者が出てきたりとか、交差点での右折時に対向車線を速度感覚が判りにくいバイクが走ってきたりとか、右または左後方の死角から歩行者が横断歩道を渡ってきたりとか・・・などなど。なかなか良くできています。
加減速と連動してシートが動いたりするけれど、Gは無いので実車の感覚で運転するのは結構難しいです。
第二段階の実地教習は、大型免許所有者の場合は10時間なんだけど、そのうちシミュレーター教習で4時間取られるので、実際に路上に出るのは6時間しかない。少ない路上教習で基本的なバスの運転をしっかりできるようにならないといけないのだが・・・。規定時間で見極めもらえるのか、ちょっと心配です(汗)
まぁ頑張るしかないんですけどね(苦笑)
 それから、これが実地教習で使っているバスでございます。先日、教習が始まる前に撮影。
それから、これが実地教習で使っているバスでございます。先日、教習が始まる前に撮影。
関西方面で実際に営業運転で使われていた車両で、中古で購入後に教習仕様に改造したもの。スピードメーター下の距離計を見てみると、走行距離は60万キロを超えています。
大型トラックではもっと走っている車両もありますが、短距離での発進→停止を繰り返すバスなので、指導員の話によると「結構各部が痛んでいる」そうです。走っている感じはあまり痛んでいる感じはしないんですけどね。
前にも書いたけど、私の場合は大型免許を持っているので仮免許は不要。しかし大型車で公道を走るのは久しぶりなので緊張しました。
しかも私の通っている教習所は主要道路に出る道は事実上一本しかなく、しかもその道が大型車と普通車のすれ違いが困難な道幅しか無い区間が多く、路上一発目でここを走るだけでもかなり緊張しました。
一番キツかったのは、その狭い道で電線の工事を行っており、工事車両の脇はバスで通過不能だった事(*_*)
工事車両が移動してくれたので、何とか通る事ができましたけど・・・。
とにかく先読み先読みで走り、狭い区間や障害物のある区間は対向車を先にやり過ごさせるようにしないと、バスやタクシーでは御法度の急ブレーキを掛ける羽目になりかねない。急ブレーキは即車内事故に直結する(当然その責任は運転手が負う)ので、教習とは言えやってはいけないのだ。
しかも大型車の場合は車幅が広い上に、ミラーが高い位置で車両本体からはみ出しているので道路脇の民家の軒先とか街路樹に当たりそうになるし、普通車より遥かに気を使います。
主要道路に出れば道幅の心配はしなくて良いんだけど、コース内と違って安全確認はキッチリやらないと、普通車はもちろん平ボディ(荷台に箱の付いていない)トラック以上に死角の多いバスの場合はマジで危険が伴う。かなり緊張しながらハンドルを握っていました。
何といっても一番神経を使うのは、交差点での左折時。左後方から横断歩道に入ろうとする歩行者や自転車はミラーはもちろん目視でもほとんど見えないので、目一杯徐行しないと本当に危険。これも交差点に近づく段階であらかじめ確認が必要。右折なら後方の自転車や歩行者は目視で簡単に確認できるんですけどね。
公道をバスで走って何が一番怖いかというと、自転車と歩行者が一番怖いです。どんな動きをするか分からないし、車からは自分が見えていると思っている場合がほとんどだし、万が一の場合は責任取るのは車のほうだし・・・。
交差点も含めてこれは普通車でも同じなんだけど、普通車やトラックとは違い『急ブレーキを踏めない』という事情を抱えたバスやタクシー等旅客を乗せる車両を運転していると、周りの歩行者と自転車と車の動きに神経質にならざるを得ません。
あと、上り坂ではやはりスピードは出ませんでした。3速ではエンジンが吹け切ってしまい、4速ではトルクが不足気味で加速できない・・・という感じ。結局3速で登るんだけど、制限速度まで出せないという状態でした。後続車の皆さん、ごめんなさい。
バスならではの路上での課題として、路肩の電柱や標識や街灯をバス停に見立てて路肩停車(車両自体は本物のバスとは言え教習車は営業車両ではないので、バス停には停車禁止)・・・というものがある。
これにも「乗降口を(仮)バス停にきちんと揃えて停車し、ウィンカーはハザードにし、ギヤはニュートラルにしてクラッチを戻し、サイドブレーキを引いて、停車から発車までブレーキペダルは踏みっ放しにする」という手順がある。乗降口を開けるのは、サイドブレーキを引いた後。
(仮)バス停と乗降口を揃えるのは、コース内と勝手が違ってややズレてしまったんだけど、何とか今日のところはクリアできた。卒業検定でも必ずやるので、この辺りはしっかりできるようにならないといけない。
今日の反省点としては、制限速度を超えてしまった事が何回かあった事と、直進中に左側に寄り過ぎて路側帯のラインを踏んでしまう事が多々あった事。次回はそれを意識して修正していかねば。
で、今日二時間目の実地はシミュレーター。乗客を乗せて目的地まで乗客の指示と案内標識に従って走行するというもの。
この教習は「急ごうとする心理の悪影響」を体験する為のもので、走っていると後ろの乗客から「急いでもらえませんか?」と催促されたり、前が詰まっている状態で後ろのスポーツカーがパッシングを浴びせてきたりする。
更に、自分の走行状態に合わせて駐車車両の影から歩行者が出てきたりとか、交差点での右折時に対向車線を速度感覚が判りにくいバイクが走ってきたりとか、右または左後方の死角から歩行者が横断歩道を渡ってきたりとか・・・などなど。なかなか良くできています。
加減速と連動してシートが動いたりするけれど、Gは無いので実車の感覚で運転するのは結構難しいです。
第二段階の実地教習は、大型免許所有者の場合は10時間なんだけど、そのうちシミュレーター教習で4時間取られるので、実際に路上に出るのは6時間しかない。少ない路上教習で基本的なバスの運転をしっかりできるようにならないといけないのだが・・・。規定時間で見極めもらえるのか、ちょっと心配です(汗)
まぁ頑張るしかないんですけどね(苦笑)
 それから、これが実地教習で使っているバスでございます。先日、教習が始まる前に撮影。
それから、これが実地教習で使っているバスでございます。先日、教習が始まる前に撮影。関西方面で実際に営業運転で使われていた車両で、中古で購入後に教習仕様に改造したもの。スピードメーター下の距離計を見てみると、走行距離は60万キロを超えています。
大型トラックではもっと走っている車両もありますが、短距離での発進→停止を繰り返すバスなので、指導員の話によると「結構各部が痛んでいる」そうです。走っている感じはあまり痛んでいる感じはしないんですけどね。